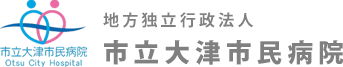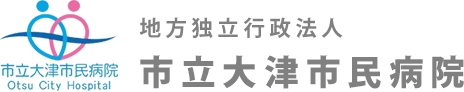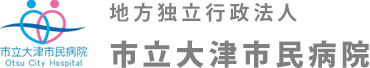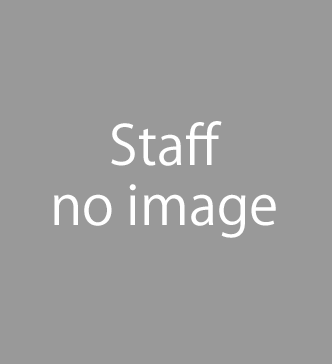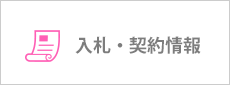診療科・部門一覧
一般・乳腺・消化器外科
診療内容・特色
当診療科はすべての外科領域疾患に対応し、地域の方々の医療福祉に貢献できるように日々努力しています。また24時間オンコール体制により、虫垂炎、腹膜炎や鼠径ヘルニア嵌頓などに対する緊急手術に備える一方、食道がん・胃がん・大腸がんなどの消化管がん、肝臓がん・膵がんなどの肝胆膵領域がんに対し、ガイドラインとエビデンスに基づいたハイレベルな外科治療を、患者さんひとりひとりのご要望に応じて提供できるよう、工夫しています。ヘルニア、肛門疾患(痔疾、直腸脱)などの身近な疾患にも力を入れています。
最も力を入れているポイントは、徹底した低侵襲手術を心がけていることです。患者さんに痛みやダメージを与えない内視鏡手術をあらゆる領域で積極的に導入しており、他院と比べても内視鏡手術の比率はかなり高いものとなっています。また当院には日本内視鏡外科学会技術認定医も在籍しており、胃がん・結腸・直腸がんに対するロボット支援手術も行っています。
さらに当院の放射線治療の導入に伴い、がんに対する集学的治療を完全に行える体制が整っています。
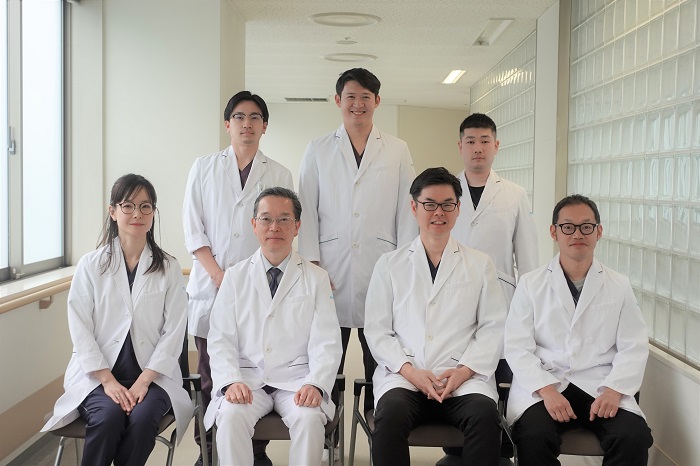
当診療科は日本外科学会専門医制度修練施設・指定施設、日本消化器外科学会専門医制度指定修練施設・認定施設です。日本内視鏡外科学会技術認定医および日本肝胆膵外科学会高度技能指導医も在籍し、各学会専門医・指導医が患者さんの治療を行うと同時に、外科を志す研修医・外科専門医・消化器外科専門医の育成も行っています。
※また当科は大阪医科薬科大学消化器外科学教室の関連施設として、スタッフの交流や医療情報の交換を活発に行っています。
診療の特長
-
キズの小さな腹腔鏡手術を積極的に取り入れています
当科には日本内視鏡外科学会技術認定医が在籍しています。キズが小さく痛みの少ない患者さんに優しい内視鏡手術を、麻酔科の協力のもと食道がん、胃がん、大腸がん、肝がんなどの悪性疾患、胆石症、食道裂孔ヘルニアや鼠径部ヘルニア、腹壁ヘルニアなどの良性疾患、さらに虫垂炎や急性胆のう炎、腸閉塞などの救急症例を含め、可能な限り積極的に施行できる体制を整えています。さらに胆嚢摘出術に対しては、従来の腹腔鏡手術に比べても術後疼痛と整容性の面で優れている単孔式手術を行っております。 -
手術支援ロボットを用いた胃がん・直腸がん手術
腹腔鏡手術には上記のような利点が多くありますが、固定された小さなポート創から直線的な器具で操作を行うという制限があります。手術支援ロボットを用いた内視鏡手術では、こうした難点を克服してがんの切除手術で要求される繊細な操作を確実に行うことができます。当科では現在ロボット支援胃がん・結腸・直腸がん手術を行っております。 -
肝胆膵領域の高度進行がんの手術
当科には日本肝胆膵外科学会高度技能指導医が在籍しています。切除困難な肝臓がん、胆管がん、膵臓がんなどの肝胆膵領域疾患に対しても、十分な手術器材、麻酔科とICUによる充実した管理体制を備え、関係各科と協力のうえ積極的な切除を行っています。 -
完全内視鏡下食道がん手術
食道がん手術は、がん切除術の中でも最も侵襲性が高く、合併症発生率が高い手術です、少しでも体に与える影響を軽減するために、内視鏡手術が取り入れられてきましたが、食道周囲には気管や大動脈などの重要臓器が多く、安全な手術には豊富な経験と専門的知識が欠かせません。当院では大きな切開を入れない「完全内視鏡下食道がん手術」を安全に施行しつつ、化学療法、化学放射線療法を組み合わせて、根治を目指す安全な食道がん治療を提供しています。 -
小児、成人に対する腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術
当科での成人鼠径ヘルニア手術の第一選択は腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術(TAPP)で、成人鼠径部ヘルニアの約80%に施行しています(腹腔鏡下手術は鼠径部ヘルニア診療ガイドラインでは推奨グレードB)。入院期間は1~3日と短縮滞在での治療を可能としています。
小児鼠径ヘルニアは成人での手技を応用し腹腔鏡下手術(LPEC)を導入しています。未だ症例数は少ないものの滋賀県下で最初に導入しました。LPECは日帰り手術可能で、日常生活を大きく変えることなく手術を受けることができます。 -
総合病院が行う肛門手術
肛門疾患には様々な種類がありますが、実際には悪性腫瘍や泌尿器系もしくは婦人科系の疾患(病気)が隠れていることもあり総合的に判断・治療をする必要があります。また、排便機能や排尿機能に関連する部分であり将来を考えて治療をする必要もあります。当院では外科専門医が総合病院の特色を活かし他科との連携をとり悪性腫瘍を含め様々な疾患に対応できます。 -
注射による痔核の治療
当科では、痔核は「切らずに治療」を原則としており、ジオン注による硬化療法を導入しています。当科には2名の四段階注射法(ジオン注)修得医が在籍し痔核の治療に携わっています。その他、痔瘻・裂肛・直腸脱などあらゆる肛門疾患に対応しています。 -
エビデンスに基づいた化学療法
ガイドラインに基づいた消化器がん、乳がんに対する化学療法を積極的に行っています。当初切除不可能であった腫瘍であっても、化学療法が奏功して切除できる症例も多くあります。他院で手術を受けられた患者さん、他院で化学療法を行っている患者さんも受け入れ可能です。


専門外来
-
乳腺外来
当院では、2名が診療にあたっております。
受診当日に、マンモグラフィ検査または乳腺超音波検査を施行し、その結果は当日に説明します。良性・悪性の鑑別のため精密検査が必要な場合は、細胞診や針生検も当日に行うことが可能です。
乳がんと診断された場合、乳房再建を含めた手術療法・薬物療法・リハビリテーション・心のサポートなどを当院で受けていただくことが可能です。
乳がんが心配な方や、乳房に関してお悩みの方は、症状の有無に関わらずお気軽に当院を受診してみて下さい。
■曜日:月曜日・水曜日・木曜日・金曜日 -
女性外科外来(小児鼠径ヘルニアにも対応しています)
女性外科外来では、乳腺疾患のほか、痔や肛門病変、鼡径ヘルニアなど、男性医師に相談しにくい疾患や、恥ずかしさから女性にとって受診のハードルが高い疾患について、女性医師が対応いたします。
小児鼡径ヘルニアにも対応していますので、ご自身が受診される際にご相談ください。
安心して受診いただけるよう、プライバシーにも十分配慮しています。
■曜日:月曜日 -
Express外来
”進行がん”と診断されても速やかに検査し、最短10日で手術までおこないます。
消化器がんの治療は、いくつかの精密検査の結果を総合した診断によって方針が決定されます。
我々は、消化器外科・内科・放射線科の専門医を中心に、速やかに患者さんの治療に臨みたいと考えております。
初診日(少なくとも2-3日以内)に、血液検査・造影CT・内視鏡検査ならび手術に必要な心電図・呼吸機能検査・レントゲン検査など治療方針の決定に必要な検査を行い、専門医師により治療方針についてお話しさせていただきます。
また手術が必要な場合は、手術日の決定までおこないます。
■曜日:毎日 -
救急外来
当科ではあらゆる外科領域の疾患に対して24時間対応できる体制をとっております。昼夜を問わず、虫垂炎や腸閉塞など緊急手術を要する場合でもご遠慮なくご相談ください。
主な症例(手術)と件数、臨床実績
手術症例数推移(各年1月~12月)
(単位:例)
| 手術数 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 全手術数 | 495 | 460 | 441 |
| 鏡視下手術(EMR・ESDは除く) | 342 | 265 | 267 |
| 全麻手術数 | 408 | 405 | 384 |
| 緊急手術数 | 81 | 110 | 112 |
(単位:例)
| 術式別手術数(そのうち鏡視下数) | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|
| 食道切除術 | - | 0(0) | 2(2) | 1(1) |
| 幽門側胃切除術 | (幽門保存含む) | 12(10) | 18(18) | 9(7) |
| 胃全摘術 | (噴門含む) | 7(5) | 3(1) | 4(2) |
| 胃部分切除術 | - | 3(2) | 4(3) | 4(4) |
| 結腸切除術 | - | 53(38) | 32(26) | 35(24) |
| 直腸切除術 | - | 25(21) | 24(23) | 31(29) |
| 直腸切断術 | (骨盤内蔵全摘含む) | 2(2) | 0(0) | 1 |
| 乳がん手術 | - | 29 | 48 | 8 |
| 胆のう摘出術 | (総胆管切石術含む) | 82(79) | 80(78) | 80(75) |
| 虫垂切除術 | - | 38(38) | 43(43) | 37(36) |
| 成人ヘルニア手術 | (鼡径・大腿・腹壁ヘルニア) | 78(68) | 97(64) | 59(50) |
| 小児ヘルニア手術 | - | 0 | 0 | 0 |
| 良性肛門疾患手術 | (痔核・脱肛など) | 22(1) | 20(1) | 32 |
肝胆膵領域の手術実績(手術件数)
肝切除術(肝臓がん・胆のうがん・胆管がんなどに対する)
| 術式別手術数(そのうち鏡視下数) | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 葉切除以上 | 2 | 7 | 1 |
| 区域切除・亜区域切除・外側区域切除 | 5 | 1 | 2 |
| 部分切除(肝床部切除含む) | 9(1) | 16(6) | 13(7) |
| 総数 | 16(1) | 24(6) | 16(7) |
膵切除術(膵臓がん・IPMNなどに対する)
| 術式別手術数(そのうち鏡視下数) | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 膵頭十二指腸切除術 | 3 | 6 | 0 |
| 膵体尾部切除術 | 2 | 4(0) | 3 |
| 膵全摘術 | 0 | 0 | 0 |
| 膵中央切除術 | 0 | 0 | 0 |
| 膵部分切除術 | 0 | 0 | 0 |
| 上記のうち血管再建を伴うもの | 0 | 0 | 0 |
| 総数 | 5 | 10(0) | 3 |
スタッフ紹介・学会認定医等資格

田中 慶太朗
| 役職 | 一般・乳腺・消化器外科統括診療部長 (副院長) |
|---|---|
| 学会認定医等資格 | 日本外科学会専門医・指導医・代議員、日本消化器外科学会専門医・指導医、日本内視鏡外科学会評議員・技術認定医・ロボット支援手術認定プロクター、日本大腸肛門病学会専門医・指導医・評議員、日本癌治療学会代議員、日本がん治療認定医機構がん治療認定医、日本消化器内視鏡学会専門医・指導医、日本消化器病学会専門医、日本ロボット外科学会認定医、日本臨床外科学会評議員、近畿外科学会評議員 |
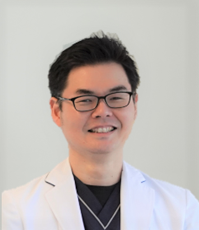
大住 渉
| 役職 | 診療部長(消化管外科部門) |
|---|---|
| 学会認定医等資格 | 日本外科学会専門医、日本消化器外科学会専門医、日本内視鏡外科学会技術認定医(大腸)、Certificate of da Vinci System Training As a Console Surgeon、日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医、日本消化器内視鏡学会専門医・指導医、日本消化器病学会専門医、日本ロボット外科学会専門医(国内B)、近畿外科学会評議員 |
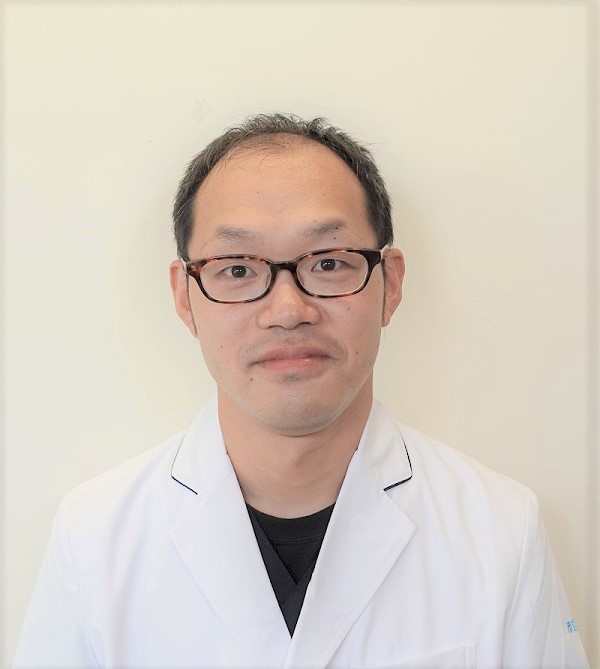
駕田 修史
| 役職 | 診療部長(肝胆膵外科部門) |
|---|---|
| 学会認定医等資格 |
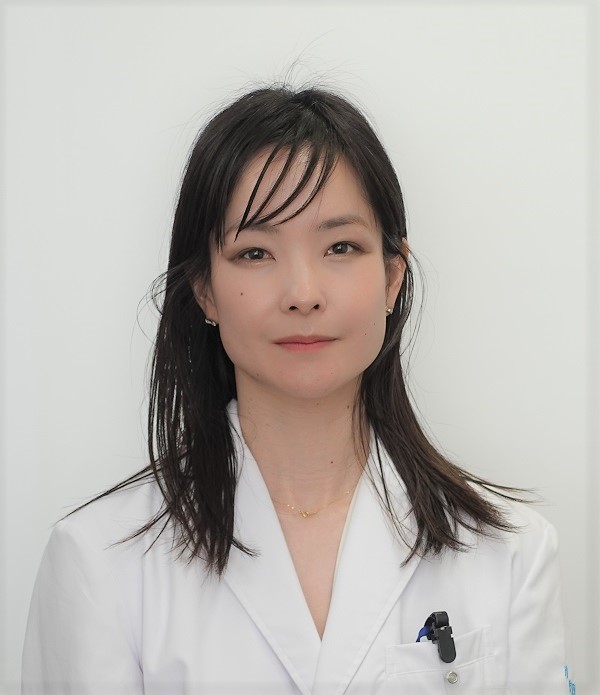
川口 佳奈子
| 役職 | 診療部長(乳腺外科部門) |
|---|---|
| 学会認定医等資格 | 日本外科学会認定外科専門医、日本乳癌学会認定乳腺専門医、日本乳がん検診精度管理中央機構認定検診マンモグラフィ読影認定医、乳がん検診超音波検査実施・判定医、近畿外科学会評議員 |
大西 春佳
| 役職 | 医員(乳腺外科) |
|---|---|
| 学会認定医等資格 | 日本外科学会認定外科専門医 |
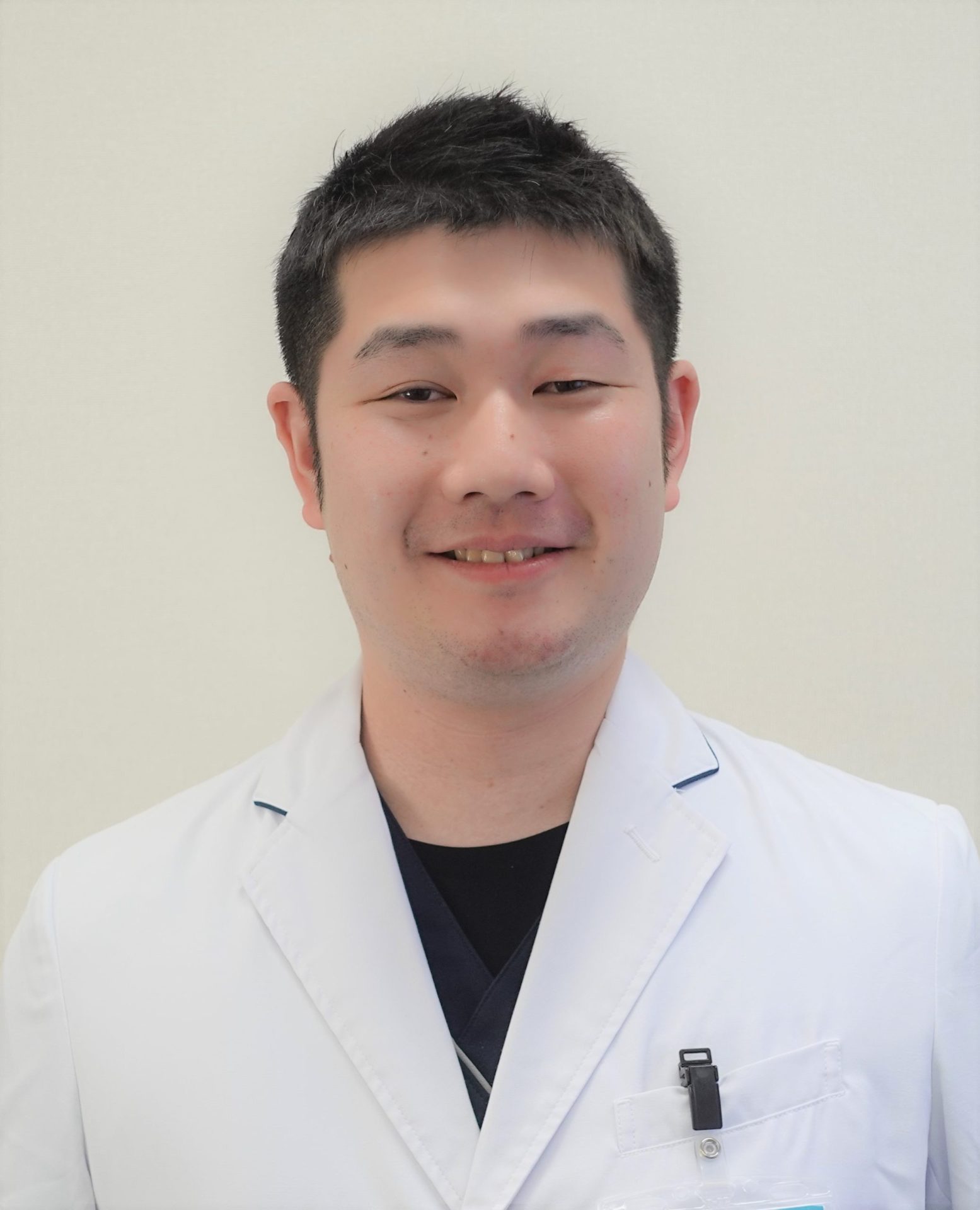
堀口 晃平
| 役職 | 専攻医 |
|---|---|
| 学会認定医等資格 |
岸 剣太郎
| 役職 | 専攻医 |
|---|---|
| 学会認定医等資格 |
学会指導施設認定
日本外科学会専門医制度修練施設・指定施設
日本消化器外科学会専門医制度指定修練施設・認定施設
外来診療担当表
診療受付時間 8:30~11:30(診療時間 8:45~17:15)
- 医師の都合により、休診または代診となる場合があります。予めご了承下さい。
- 午後の診療は、原則として予約となっておりますので、詳しくは外来受付窓口へお問合せ下さい。
- 赤字は女性医師です
一般・消化器外科
| 診察場所 | 診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1診 | B2-1 | 午前 | 田中 | 富山 | 大住 | 交代制 | 駕田 |
| 午後 |
|
||||||
| 3診 | B2-4 | 午前 | 堀口 | 岸 | |||
| B2-3 | 堀口 (第1,3,5週) 岸 |
||||||
| 2診 | B2-2 | 午前 |
女性外科外来 |
女性外科外来 (予約制) |
|||
乳腺外科
| 診察場所 | 診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2診 | B2-2 | 午前 | 川口 (兼女性外科外来) |
川口 (兼女性外科外来) |
大西 | 大西 | |
| 午後 | |||||||
急な発病や、症状の急な変化に対しては随時対応しておりますので、受付でお申し出ください。
- 外来再診予約や、乳腺疾患の診察予約は市立大津市民病院外来Bブロック受付で行っております。
電話での予約も可能ですので、ご連絡ください。