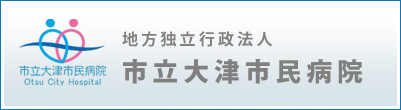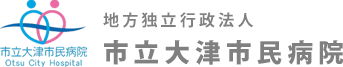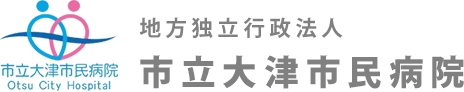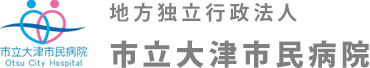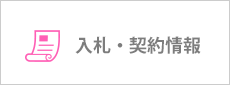診療科・部門一覧
小児外科
診療体制
小児外科では、医師2名体制(共に非常勤)で小児外科疾患に対して日帰りや1泊入院での手術を行っております。麻酔科医、手術室、小児科医および小児科病棟との連携も充実しており、安心して手術をお受けいただけます。2023年12月から現在の診療体制をスタートし、2025年5月末で小児外科の手術件数が180件を超えました。今後も安心・安全な手術を行い、地域の子どもを支えて参ります。
小児外科でよく見られる疾患のご紹介
鼠径(そけい)ヘルニア
鼠経ヘルニアは、乳幼児から学童期まで幅広い年齢で見られる病気ですが、特に生後数か月から1歳頃までの赤ちゃんに多くみられます。足の付け根あたりがふくらんで見えるのが特徴で、泣いたり、おなかに力を入れたりすると目立ちます。これは腸などの一部が一時的に皮膚の下に飛び出しているためです。通常は痛みがないものの、まれにふくらみが戻らなくなり、強い痛みや吐き気を伴う「嵌頓(かんとん)」という状態になることもあります。その場合は緊急手術が必要になるため、ふくらみに気づいたら早めに小児外科を受診してください。治療は従来から行っている鼠径部を切開する方法や腹腔鏡を用いた方法で行い、短時間で済みます。
臍(さい)ヘルニア
臍ヘルニアはいわゆる「でべそ」のことで、新生児から生後数か月の乳児期に多く見られる状態です。おへその奥にある筋膜と筋肉が完全に閉じておらず、おなかの圧力によって腸が押し出されることで、おへそがふくらんで見えます。まずはおへその膨らみを戻しておへそが膨らまないように綿球で圧迫する綿球圧迫療法を行います。ほとんどの場合は、成長に伴って1歳頃までに自然に治ることが多いですが、ふくらみが大きく外見上目立つなど改善が見られない場合は、手術を検討することがあります。手術は短時間で済み、見た目にも配慮した丁寧な対応が可能です。
停留精巣(ていりゅうせいそう)
停留精巣は、新生児期に指摘される疾患で、精巣が陰嚢(いんのう)におりてこないまま、おなかの中や足の付け根にとどまっているものです。生まれてすぐにはわかりにくいこともありますが、健診などで見つかることが多く、生後1歳頃までは自然に降りてくることもあります。陰嚢までの下降が確認できない場合、将来の健康や生殖機能への影響を避けるため、1歳〜1歳半頃までに手術を行うことが推奨されています。
舌小帯短縮症(ぜっしょうたいたんしゅくしょう)
舌小帯短縮症とは、舌の裏側にある「舌小帯(ぜっしょうたい)」という膜状の組織が短かったり、ついている位置が前すぎたりすることで、舌の動きが制限されてしまう状態です。新生児期や乳児期に発見されることもありますが、はっきりとした症状が見られるのは離乳期や幼児期以降になることもあります。哺乳しづらい、離乳食が食べにくい、発音が不明瞭、といった症状で気づかれることが多く、見た目としては舌がハート型に見える場合もあります。すべての舌小帯短縮症が治療対象ではありませんが、機能的な問題がある場合には、短い舌小帯を切開する「舌小帯形成術(せっしょうたいけいせいじゅつ)」を行うことがあります。手術は短時間で済みます。滑舌が悪い場合には術後当院のリハビリテーション部で口や舌の筋肉を動かす訓練を行う事もあります。
スタッフ紹介・学会認定医等資格
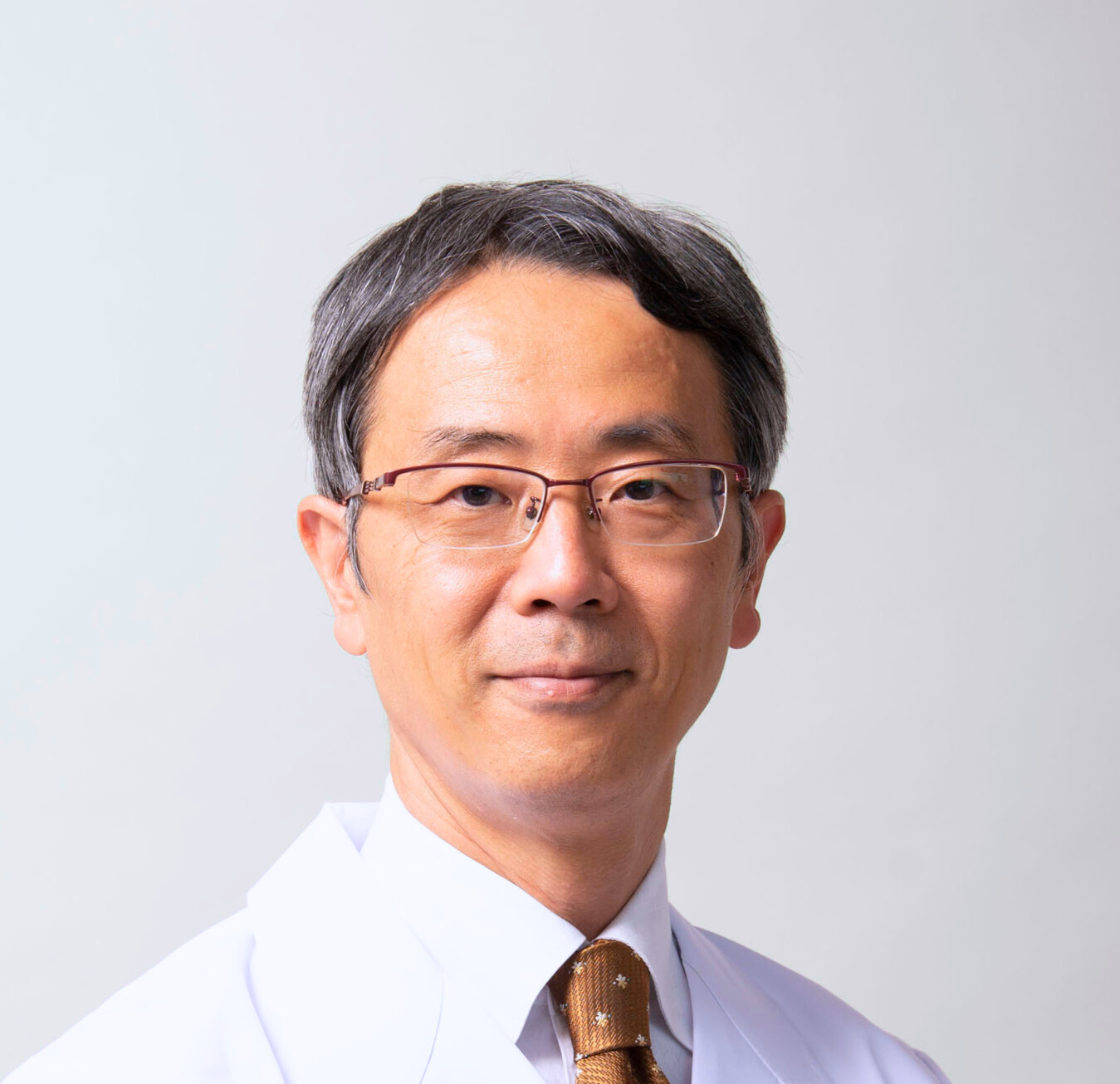
富山 英紀
| 役職 | 非常勤医師 |
|---|---|
| 学会認定医等資格 | 日本外科学会専門医、日本小児外科学会専門医、近畿外科学会評議員、小児外科近畿地方会評議員 |

佐々木 康成
| 役職 | 非常勤医師 |
|---|---|
| 学会認定医等資格 | 日本外科学会専門医、日本小児外科学会専門医、近畿外科学会評議員、小児外科近畿地方会評議員 |
外来診療担当表
| 診察場所 | 診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2-1 | 午前 | 富山 | |||||
| D | 午前 | 佐々木 | |||||
- 火曜日、水曜日のみの診療となります。
- 非常勤体制のため、緊急性のあるものは対応が困難な場合もありますので、地域医療連携室へお問合せ下さい。