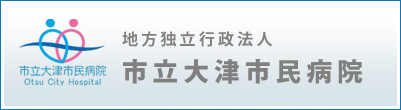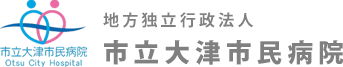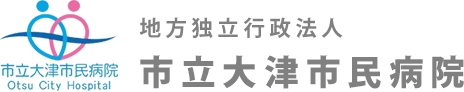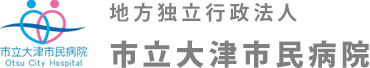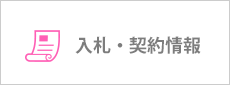診療科・部門一覧
一般検査
尿、糞便、体腔液(胸水、腹水、心嚢液、関節液)、髄液などを検体として、性状や成分量を観察、分析することで病態の把握を行います。尿検査や便検査は身体への負担をあまりかけることなく繰り返し検体を採取できる検査であり、病態を推測するためのスクリーニング検査や治療経過、薬の副作用を把握できるとして広く行われています。
尿定性検査
尿試験紙を用いて尿蛋白、尿糖、尿潜血などといった成分の定性と半定量値を調べることにより腎・泌尿器系を中心に、肝・胆疾患や糖尿病などの全身の生理・生体異常の有無を推測し治療の経過を予測するための判断材料として利用されています。
尿沈渣検査
尿は腎臓の糸球体で血液が濾過されて生成され、尿管→膀胱→尿道を経由し体外へ排出されます。尿中に出現した赤血球、白血球、上皮細胞、円柱類、細菌などの微生物や結晶などの有形成分を、自動分析機で分析したり、遠心分離機で集めた細胞成分を顕微鏡下で質的、量的に観察することで腎・泌尿器系病変や腫瘍細胞の有無を確認したり、全身性の系統的疾患の診断材料として病態把握に役立てられます。


便検査
糞便中に血液(ヘモグロビン)が含まれているかを検査することで大腸などの下部消化管からの出血の有無を調べることができます。便の表面を専用のスティックで採取し測定することで目に見えない微量な血液を検出することができ、大腸癌のスクリーニング検査として用いられます。また、腸管の炎症度を推測したり、ピロリ菌の感染診断等も実施します。
体腔液検査
心膜腔、胸腔、腹腔、関節腔などに貯留した体液を穿刺し採取された液を検査します。貯留した液の性状を調べることで液が貯留した原因や病態、他の疾患との関連を推測することができます
髄液検査
髄液は腰椎を穿刺し採取され、髄膜炎や脳炎などの中枢性疾患を診断する上で重要な検査であり、他にもくも膜下出血や脳腫瘍などの診断にも利用されます。細胞の数や形態、生化学成分を迅速に分析し、病態の早期診断、早期治療に役立てます。